一厘銅貨
1 rin (Copper)


写真のコイン:明治17年銘 直径15.7mm, 重量0.935g
データ
- 発行/通用禁止: 明治7年(1874)/昭和28年(1953)
- 製造期間: 明治6年(1873)~17年(1884)
- 発行枚数: 44,491,550枚
- 材質: 銅980 錫10 亜鉛10
- 直径: 15.75mm
- 重量: 0.91g
- 図柄: (表)「一厘」の文字、(裏)菊の紋
発行の経緯
- 幕府から新政府に大政奉還され、明治時代が始まりました。慶応4年(明治元年、1968年)には既に、貨幣の単位を文・両から円・銭・厘へと、貨幣には円形の西洋式のコインを使用する事などが決められていましたが、この間も含めて明治2年までは、旧幕府同様の貨幣を製造していました。明治4年になってようやく新貨幣の形式等を定めた「新貨条例」が公布されました。
- この新貨条例により試鋳された明治3年銘の試鋳貨は、写真のものとは図案が異なっており、「一厘」は横書きで真ん中に旭日が配されています。また、菊紋の面も「大日本・1RIN」の代わりに「十枚換一銭」の文字が記されています。このデザインの一厘は結局発行されませんでした。
- 実際の発行は明治7年からになりますが、この際にも試鋳貨(明治6年銘)が発行されており、こちらは「1RIN」の代わりに「1MIL」と記されています。MILは1/1000(インチ)を表す言葉で、銭=centに対して表記されようとしたようです。最終的にデザインは、表が大きな菊の紋章と年号と1RIN、裏は漢字で「一厘」となりました。1厘は、1/1000円, 1/10銭にあたり、1円=1両と定めた円制度では、4文にあたります。
希少性
- 明治9年と13年は非常に珍しく、何十万円もすることになっていますが、精巧なものからいい加減なものまで、相当量の偽物が出回っているみたいで、本物にお目にかかることはほぼ無いようです。デザインがさっぱりしてことも、贋作されやすい一因になっているようです。一目で偽物とわかるものも多くあります。私の持っているのはやたら厚い。
- 普通年・普通品ならば数百円で手に入れられます。余り流通しなかったのか、状態もデザインかわからないようなものは少ないと感じます。
コメント
- とにかく薄くて手で曲がりそうなコインです。でも、以外と丈夫で、戦中の錫貨幣よりはずっと丈夫です。
- 摩耗しやすい銅製のコインですが、竜銅貨に比べると摩耗していないコインが多いと感じます。
- 明治になっても少額貨幣については、江戸時代の貨幣がまだ流通していました。天保通宝(8厘通用)に至っては使用停止がのびのびになり、最終的には明治24年に回収が行われたようです。一厘は額面も安いことも併せてあまり流通せずに退蔵されていたのではないかと思っています。
- 一厘銅貨は他の硬貨と製造工程が異なると書かれています。通常の硬貨は円形に打ち抜いた金属板に、金属製の判子(極印)で打刻して製造されますが、この行程とどのように異なるのかははっきりしません。しかし、ほかの硬貨に比べて極端に薄く、硬貨の縁ももんやりしている感じで、確かにほかの硬貨とは外観が異なっています。
この時代の他の硬貨
Api 8 2022
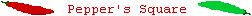

 トップページに戻る
トップページに戻る